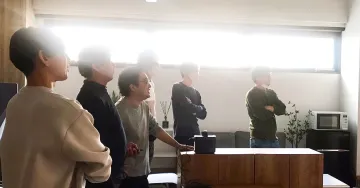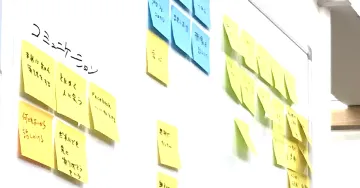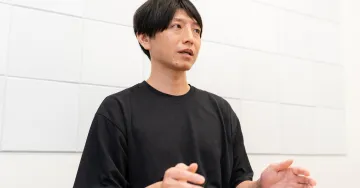「使いやすい」と感じる基準は、人それぞれ異なるもの。年齢、性別、身体能力、文化的背景など、私たちは実に多様な特性を持っています。そんな中で、「すべての人にとって使いやすい」デザインを実現するにはどうすればよいのでしょうか?
その答えとなるのが「ユニバーサルデザイン」です。近年、製品開発やサービス設計において、ますます注目を集めているこの概念。
本記事では、ユニバーサルデザインの基本的な考え方から、7つの重要な原則、身近な実例まで、わかりやすく解説していきます。
上記以外にも、さまざまなユニバーサルデザインの例をこちらの記事で紹介しています。
ビビッドソウルは、リピート率90%超の「思いやりのものづくり」を提供するWeb・システム制作会社です。
業界経験豊富なディレクターが、webサイト制作をお手伝いさせていただきます。
webサイト制作について、ご要望の方はぜひ一度ビビッドソウルまでご連絡ください。
ユニバーサルデザインの基本概念と重要性
はじめに、ユニバーサルデザインの基本概念と重要性を紹介します。
ユニバーサルデザインの定義と目的
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、身体状況など、人々の多様な個性や違いに関係なく、誰もが使いやすい製品やサービスを提供する考え方です。
この概念は1980年代に、自身も車いす生活を送っていたアメリカのロナルド・メイス教授によって提唱されました。
それまでの「バリアフリー」が、障害となる要素を見つけてから対処する考え方だったのに対し、ユニバーサルデザインは設計段階から多様な人々のニーズを考慮します。例えば、段差をなくすスロープの設置は、車いすの方だけでなく、ベビーカーを押す人や高齢者にも便利です。
日本では1990年代にこの考え方が導入され、現在では街づくりから製品開発まで、幅広い分野で活用されています。
ユニバーサルデザインの目的は、誰もが平等に社会参加できる環境を作ることです。これは単なる思いやりの形ではなく、持続可能な社会を実現するための重要な設計思想として認識されています。
バリアフリーとの違い:包括的アプローチ
バリアフリーとユニバーサルデザインは、一見似ているように感じますが、その本質は大きく異なります。バリアフリーは、既存の障壁を取り除く事後的な対応であるのに対し、ユニバーサルデザインは設計段階から多様な人々のニーズを組み込む予防的なアプローチです。
バリアフリーは主に物理的な障壁の除去に焦点を当てますが、ユニバーサルデザインは社会的、制度的、心理的なバリアまでも考慮に入れた包括的な設計思想です。
例えば、階段に後付けでスロープを設置するのがバリアフリーであるのに対し、最初から緩やかな傾斜路を設計に組み込むのがユニバーサルデザインです。このアプローチの違いは、費用対効果にも表れます。事前の包括的な設計は、後からの改修よりも効率的で経済的です。
東京2020パラリンピック競技大会を機に、日本政府は「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を策定し、街づくりと「心のバリアフリー」の両面から共生社会の実現を目指しています。
デザイナーにとってのユニバーサルデザインの意義
デザイナーにとって、ユニバーサルデザインは創造性と社会的責任が交差する重要な領域です。デザイナーは多様なユーザーのニーズを理解し、創造的なソリューションを提供することで、社会に大きな価値をもたらすことができます。
ユニバーサルデザインは単なる社会貢献ではなく、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。デザイナーは、使いやすさと魅力的なデザインの両立を追求することで、より多くの人々に価値を提供できるのです。
ユニバーサルデザインの7原則とその応用
次に、ユニバーサルデザインの7原則とその応用を紹介します。

公平性:誰もが使いやすいデザイン
ユニバーサルデザインの第一原則である「公平性」は、誰もが同じように利用できることを重視します。
公平性の具体的な要件は、誰もが同じ方法で使えること、差別感を与えないこと、プライバシーへの配慮、そして魅力的なデザインであることです。
身近な例として、自動ドアや段差のない歩道があります。これらは年齢や身体能力に関係なく、誰もが自然に利用できる設計です。また、階段と併設されたスロープは、車椅子利用者や高齢者にも移動の自由を提供します。
心理的な障壁を取り除くことも重要です。多言語表記の案内板や、文字サイズを調整できるウェブサイトは、外国人観光客や視覚障害者にとって大きな助けとなります。
このように公平性を意識したデザインは、利用者が特別な配慮を受けていると感じることなく、自然に社会参加できる環境を作り出します。使う人の立場に立って、誰もが快適に利用できる設計を心がけることが、ユニバーサルデザインの基本となるのです。
柔軟性:個人の好みや能力に対応
柔軟性は、ユニバーサルデザインの重要な原則の一つです。使う人それぞれの好みや能力に合わせて、柔軟に対応できる設計が求められます。
ハサミや包丁などの道具では、右利き・左利きの両方に対応した設計が採用されています。これにより、利き手に関係なく快適に使用できます。公共施設の階段では、複数の高さに手すりを設置することで、身長の異なる人々が安全に利用できるよう配慮されています。
デジタル機器の分野でも柔軟性は重視されています。スマートフォンやタブレットでは、文字の大きさや明るさ、コントラストを調整できる機能が標準装備され、視覚特性の異なる利用者に対応しています。
このような柔軟な設計により、製品やサービスの汎用性が高まり、より多くの人々が快適に利用できる環境が整います。使用者の多様なニーズに応える柔軟性は、ユニバーサルデザインの実現に欠かせない要素なのです。
直感的で分かりやすい使用法
ユニバーサルデザインにおける「直感的で分かりやすい使用法」は、誰もが特別な知識や経験がなくても、すぐに理解して使えることを重視します。
その代表例が、シャンプーとリンスのボトルです。シャンプーボトルの側面には、目の不自由な方でも触って区別できるよう、ギザギザの凹凸が付けられています。
エレベーターの操作パネルでは、階数ボタンの配置を直感的に理解できるよう、数字を大きく表示し、さらに点字も併用。緊急ボタンは赤色で目立たせるなど、視覚的な工夫も施されています。
公共施設のサインでは、言語に依存しないピクトグラム(図記号)を活用し、トイレや非常口などの場所を、誰もが一目で把握できるようにしています。
このように、直感的な使用法を実現するデザインは、利用者の負担を減らすだけでなく、安全性の向上にも貢献しています。
身体的負担の軽減とスペースの確保
ユニバーサルデザインにおいて、身体的負担の軽減とスペースの確保は重要な要素です。身体的負担を軽減する例として、センサー式の自動販売機が挙げられます。これは、高い位置の商品を選ぶ際の負担を減らすため、下部に商品選択ボタンを設置しています。
また、開けやすい歯磨き粉のキャップや、軽い力で操作できるセンサー式の水栓など、日常生活での負担を軽減する工夫も広がっています。
スペースの確保については、多目的トイレが代表的な例です。車いすの回転スペースを確保し、オストメイト対応の設備や、おむつ交換台を設置することで、多様なニーズに応えています。駐車場でも、車いす使用者や高齢者、子ども連れの方々が安全に乗り降りできるよう、十分な幅を持つ区画が設けられています。
このように、身体的負担の軽減とスペースの確保は、あらゆる人が快適に過ごせる環境づくりの基本となっています。
身近に見つかるユニバーサルデザインの例
次に、身近に見つかるユニバーサルデザインの例を紹介します。
日用品に見るユニバーサルデザイン
私たちの身の回りには、さまざまなユニバーサルデザインの工夫が施された日用品が存在します。オムロンの電子体温計「けんおんくん」は、測定中のずれを音と光で知らせる機能を搭載し、子供から高齢者まで使いやすい設計で、国際的なデザイン賞を受賞しています。
洗剤の分野では、花王のアタックZEROワンハンドタイプが、片手でプッシュするだけで適量を計量できる革新的な設計を採用しています。これにより、手に障害がある方でも簡単に洗濯ができるようになりました。
調理器具においても、ウカイ利器のUDグリップ包丁は、ハンドルの角度を変えられる設計により、手首への負担を大幅に軽減しています。また、パナソニックのアルカリ乾電池は、プラス極とマイナス極を識別しやすい色分けを採用し、誰でも簡単に正しく使用できるよう工夫されています。
このように、ユニバーサルデザインは、特別な支援を必要とする人だけでなく、すべての人が使いやすい製品づくりを目指しています。普段何気なく使用している製品にも、多くの人への思いやりが込められているのです。
公共空間でのユニバーサルデザイン
私たちの身近な公共空間でも、ユニバーサルデザインの取り組みが広がっています。JR東日本では、駅のホームドアや音声案内、多機能トイレの設置など、あらゆる利用者に配慮した設備を導入しています。
都市公園では、車椅子でも利用できる遊具や、触って植物を楽しめる感触園、休憩スペースの適正配置など、誰もが楽しめる空間づくりが進められています。
公共図書館では、点字図書や大活字本の充実、読み上げ機能付きの電子書籍端末の導入など、多様な読書ニーズに応える工夫が取り入れられています。
このように公共空間のユニバーサルデザインは、物理的なバリアの解消だけでなく、情報アクセスの平等性や心理的な快適さまでを考慮した、包括的なアプローチで実現されています。
デジタル製品とユニバーサルデザイン
デジタル製品でもユニバーサルデザインの実践が進んでいます。スマートフォンアプリやウェブサイトでは、文字の大きさ調整、色のコントラスト設定、読み上げ機能など、多様なユーザーに配慮した機能が標準装備されています。
2024年4月からの障害者差別解消法改正により、民間事業者にもウェブアクセシビリティの確保が義務化され、JIS X 8341-3規格への準拠が求められています。
企業のウェブサイトでは、シンプルで一貫性のあるレイアウト、直感的な操作性、情報の整理など、誰もが使いやすいデザインが重視されています。これらの工夫は、高齢者や障害のある方だけでなく、すべてのユーザーの利便性を向上させます。
ウェブアクセシビリティ対応は、企業の信頼性向上やブランド価値の向上にもつながり、SDGsの理念「誰一人取り残さない」の実現に貢献しています。
ビビッドソウルは、リピート率90%超の「思いやりのものづくり」を提供するWeb・システム制作会社です。
ユニバーサルデザインの実践と課題
最後に、ユニバーサルデザインの実践プロセスと課題を紹介します。
ユニバーサルデザインの導入プロセス
ユニバーサルデザインを導入するには、段階的なプロセスを踏むことが重要です。まず、基本計画の段階で施設の用途や利用者の特性を考慮し、基本方針を定めます。
次に、設計者と発注者が現場調査を実施し、利用者の視点から実際の状況を確認します。段差や出入り口の高低差、視覚障害者誘導用ブロックの配置などを詳細にチェックします。
設計段階では、移動空間や行為空間、情報提供、環境、安全性の5つの観点からチェックリストを作成し、詳細な検討を行います。特に重要なのは、サインの配置や操作性の確認、避難経路の確保です。
工事段階では、施工者がモックアップを作成し、実際の使いやすさを検証します。完成後は一定期間の利用実績を踏まえて事後評価を行い、改善点を特定します。
このように計画、設計、施工、評価の各段階で細やかな配慮を重ねることで、より多くの人にとって使いやすい空間を実現できます。得られた知見は、次のプロジェクトにも活かされ、ユニバーサルデザインの質を継続的に高めていくことができます。
ユニバーサルデザインの評価方法
ユニバーサルデザインの評価には、具体的な基準と指標が必要です。主な評価方法は、移動空間、行為空間、情報、環境、安全の5つの観点から総合的に行われます。
移動空間では、経路の連続性や見通し、案内情報の適切さを評価します。段差の解消や手すりの設置状況、十分な通行空間の確保なども重要な判断基準となります。
行為空間の評価では、室内の配置構成や家具、設備の使いやすさを検証します。特に、スイッチ類の操作性や便所の機能性については、詳細なチェックが行われます。
情報提供の面では、視覚・音声・触知情報の適切な併用状況を確認します。サインの分かりやすさや多言語対応も重要な評価項目です。
ユニバーサルデザインの今後の展望と課題
ユニバーサルデザインの未来は、デジタル社会の進展とともに大きく変化しています。2022年5月に施行された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」は、障害の種類や程度に応じた情報アクセス手段の選択を可能にし、誰もが平等に情報を得られる社会の実現を目指しています。
この法律により、音声読み上げ機能や字幕付き動画の普及が進み、情報へのアクセシビリティが向上しています。また、テキストや音声、手話など、多様なコミュニケーション手段の整備により、異なる状況にある人々の交流機会も増加しています。
一方で、デジタル技術の急速な進化は新たな課題も生み出しています。保険証のマイナンバーカードへの切り替えや確定申告の電子化など、行政サービスのデジタル化が進む中、ウェブアクセシビリティの確保が重要な課題となっています。
今後は、AIやIoT技術を活用した個別最適化されたインターフェースの開発など、より高度なユニバーサルデザインの実現が期待されています。
ユニバーサルデザインの実装はプロに依頼するのがおすすめ
ユニバーサルデザインの実装には、専門家の知識と経験が不可欠です。なぜなら、多様なユーザーのニーズを把握し、適切な解決策を提案するには、豊富な実績と専門的な見識が必要だからです。
専門のコンサルタントやデザイナーは、ユーザビリティテストの実施から、デザインの改善提案まで、包括的なサービスを提供しています。
プロフェッショナルに依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 客観的な評価基準に基づく分析と改善提案
- 多様な利用者の視点を考慮した実践的なソリューション
- 最新のデザイントレンドや技術の活用。
特に重要なのは、プロによる的確な課題抽出です。表面的な改善だけでなく、本質的な使いやすさを追求することで、より多くの人々に価値を提供できます。
ビビッドソウルは、リピート率90%超の「思いやりのものづくり」を提供するWeb・システム制作会社です。
業界経験豊富なディレクターが、webサイト制作をお手伝いさせていただきます。
webサイト制作について、ご要望の方はぜひ一度ビビッドソウルまでご連絡ください。

ゴルフ場の集客支援を行う会社で4年半ほど、WEBディレクターとしてキャリアを積みました。
お客様のビジネス成長を支援できるよう、これからも全力で取り組んでいきます。